日経平均5万円突破で「年内5万5,000円、来年3月に6万円も」 広木氏が予測する強気相場の行方
マネックス証券のチーフ・ストラテジスト、広木隆氏がマーケットのトピックや見通しなどを語る「広木隆のMonday Night Live」。ついに達成された日経平均5万円の節目について、今後の見通しや投資戦略が語られました。(※2025年10月27日収録のマネックスオンデマンドYouTube動画に基づく内容です)
日経平均5万円達成 株価は上がるもの | 広木隆のMonday Night Live 10/27
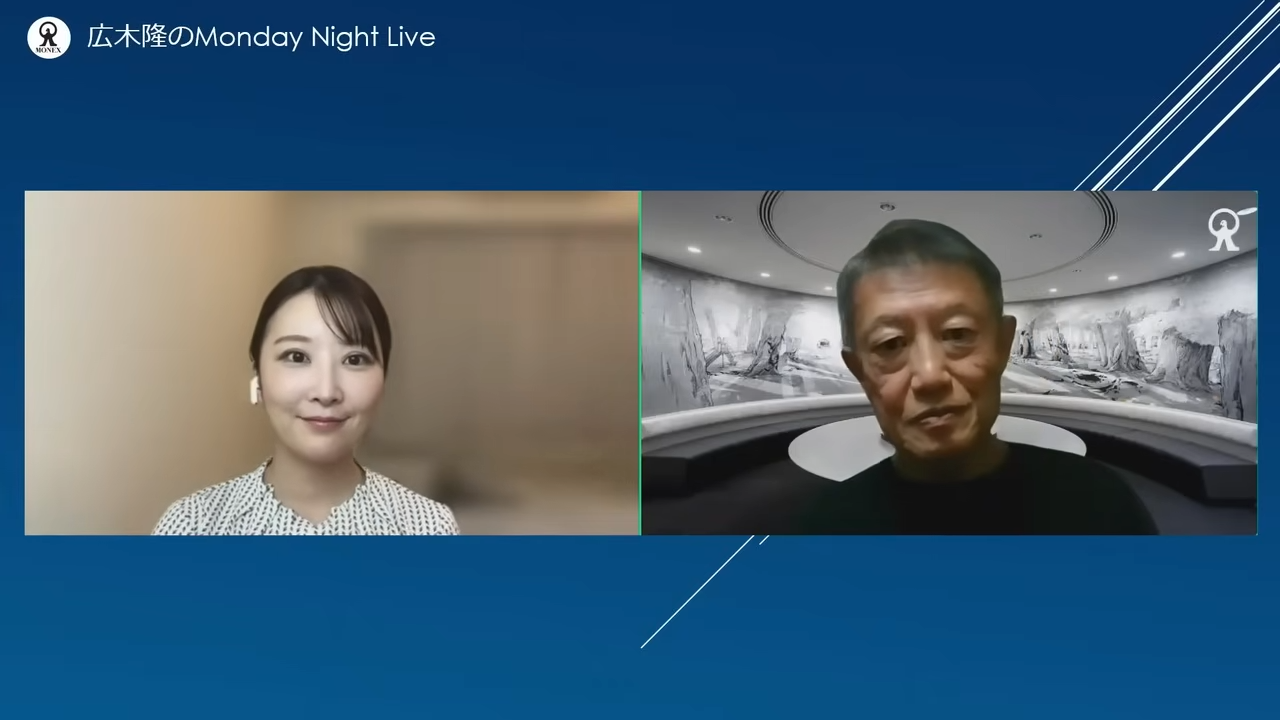
坂本麻子氏(以下、坂本):こんばんは。今夜も「広木隆のMonday Night Live」をご視聴いただきありがとうございます。本日のMCは坂本麻子が担当します。それでは広木さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
広木隆氏(以下、広木):よろしくお願いします。坂本さんとはBSテレ東の『NIKKEI NEWS NEXT』や、日経CNBCのスタジオでご挨拶したことはありますが、「広木隆のMonday Night Live」のMCは今日が初めてということで、どうぞよろしくお願いします。
坂本:こちらこそよろしくお願いします。
日経平均5万円を突破、今後の見通しは?
坂本:さっそくですが、本日(2025年10月27日)はついに、日経平均5万円を突破しましたね。
広木:そうですね。マネックス証券でも5万円突破には前から備えていました。「5万円企画」というか、5万円突破に絡んでのさまざまなコメントや読み物などをたくさんお届けしています。
私はぜんぜん記憶していなかったのですが、本日、松本大さんの5万円に寄せたコメントで、2017年の10月27日にマネックス証券が「日経平均3万円への道」というプロジェクトを始めたと書いてありました。
3万円に達した時にも、「日経平均3万円突破記念!特製Tシャツ」を作ってみなさんに配っていました。時を経て5万円に達しましたから、「日経平均5万円突破記念!特製Tシャツ」もみなさんにお届けすると思うので、楽しみにしていただければと思います。(※実際にキャンペーンとして公開されました)
坂本:日経平均5万円突破に関連して、たくさんのご質問をいただいています。「日経平均が5万円を超えました。年内どこまで上がりそうですか?」というご質問です。
広木:「今週のマーケット展望」では、「週明けから5万円をつけにいくのではないか」と書きました。今週は日米の金融政策会合など、材料が非常に多いです。そのような影響を受けて「5万円では止まらず、5万1,000円くらいまで到達するだろう」としています。そして、本日は5万円を突破し、5万500円まで到達しました。
5万円という大台に乗っただけでなく、1,000円刻みで言えば半ばまで到達しているため、「5万1,000円くらいまで到達する」という予想もあながち外れていないと考えています。
それこそ、1週間前に出演した『NIKKEI NEWS NEXT』では、高市早苗氏が女性初の総理大臣に選ばれた際、確か「5万2,000円」と示したと思います。しかし、ここまで来ると5万2,000円どころか、5万5,000円ぐらいまではあるのではないかと予想しています。
現時点でもう5万500円を超えていて、5,000円まではあと1割もなく、あり得る数字だと思います。5万3,000円や5万4,000円、場合によっては5万5,000円もあると思います。このあたりの数千円刻みはほとんどブレの範囲ですが、「5万5,000円くらい」と言っておきます。
坂本:年内5万5,000円に到達しそうということですが、「6万円に到達するのはいつになりそうでしょうか?」というご質問です。
広木:年明けの2026年3月くらいではないでしょうか。今年度末にも、という可能性も十分にあると思います。来年2026年になれば、6万円になっているのは当たり前の世界だと思います。
循環物色が支える健全な相場
坂本:「日経平均5万円突破で怖いものなしになっています。強い銘柄が利確されても割安株が探されて投資され、結果としてそちらも上がり、株式市場にお金が留まるという解説を見たのですが、そのような相場はありますか?」というご質問です。
広木:そのような相場が一番健全で、今もその状況になりつつある気がします。
一部の指摘で言えば、AI関連銘柄、例えばソフトバンクグループやアドバンテストだけが買われていくような、かなりいびつな相場じゃないかとは言われますが、実はそうではなく、けっこう幅広く循環的に物色されています。
例えば、少し前まではイオンのような、国内の内需系スーパーなどの株が高値をつけにいったり、一時的に銀行株が買われたりしました。さらに、自動車や、「高市銘柄」とされる防衛関連など、物色の対象は広がってきています。
日経平均は構成銘柄のウェイトが大きいため、ソフトバンクグループやアドバンテストが買われれば、それらが引っ張って日経平均の上昇が際立ちます。しかし、TOPIXもきちんと右肩上がりになってきており、全体的に循環的な物色が起きてきている相場であると思います。
今後の調整材料とリスク要因
坂本:「米中貿易摩擦の件もトランプ大統領の駆け引きに過ぎず、株価はすぐに戻します。今後の調整材料は国内、海外のどちらにあるでしょうか?」というご質問です。
広木:どちらにも要因がありますが、海外でいえば、米中交渉は結局二転三転します。これに振り回されて相場は少し見切っていますが、唐突にそうした動きが出ると、大きく動揺する場面もあります。
また、米国経済の動向も影響します。先週末の僕の「ストラテジーレポート」でAI不況について書きましたが、同じタイミングで日経新聞も報じており、各所でAIの負の側面が話題になっています。そのような影響が、アメリカの経済指標、特に労働市場や雇用統計などで、予想以上に早く出てきてしまうことがあります。その際は、マーケットが水を浴びせられるような展開になってしまいます。
一方、日本では、利上げに対する受け止めがしっかり消化されていない中で、日銀が追加利上げに踏み切るような場合、やはりリスクはあります。国内外ともに調整局面は入り得るとして、心の準備はしっかりしておきましょう。
日本株と米国株の投資配分
坂本:「日経平均は5万円を超え、広木さんのお話のとおりになりました。今後、米国株、マグニフィセント・セブン、日本株には、どのような割合で投資したら良いとお考えですか?」というご質問です。
広木:「これが一番良い」というものはわかりませんが、それぞれの良さがあります。やはり日本人であれば、半分は日本株で円建て資産、半分は米国株でしょうか。その米国株の中で今、特に経済を牽引しているのがマグニフィセント・セブンなので、そこに米国株の半分程度を投資するのはいかがでしょうか?
米国株のほとんどすべてをマグニフィセント・セブンにしても良いかもしれませんが、実際、その時価総額ウェイトで見れば「S&P500=マグニフィセント・セブン」と言っても過言ではないので、そう考えると日米半々ぐらいの比率で良いのではないかとは思います。
金(ゴールド)への投資戦略
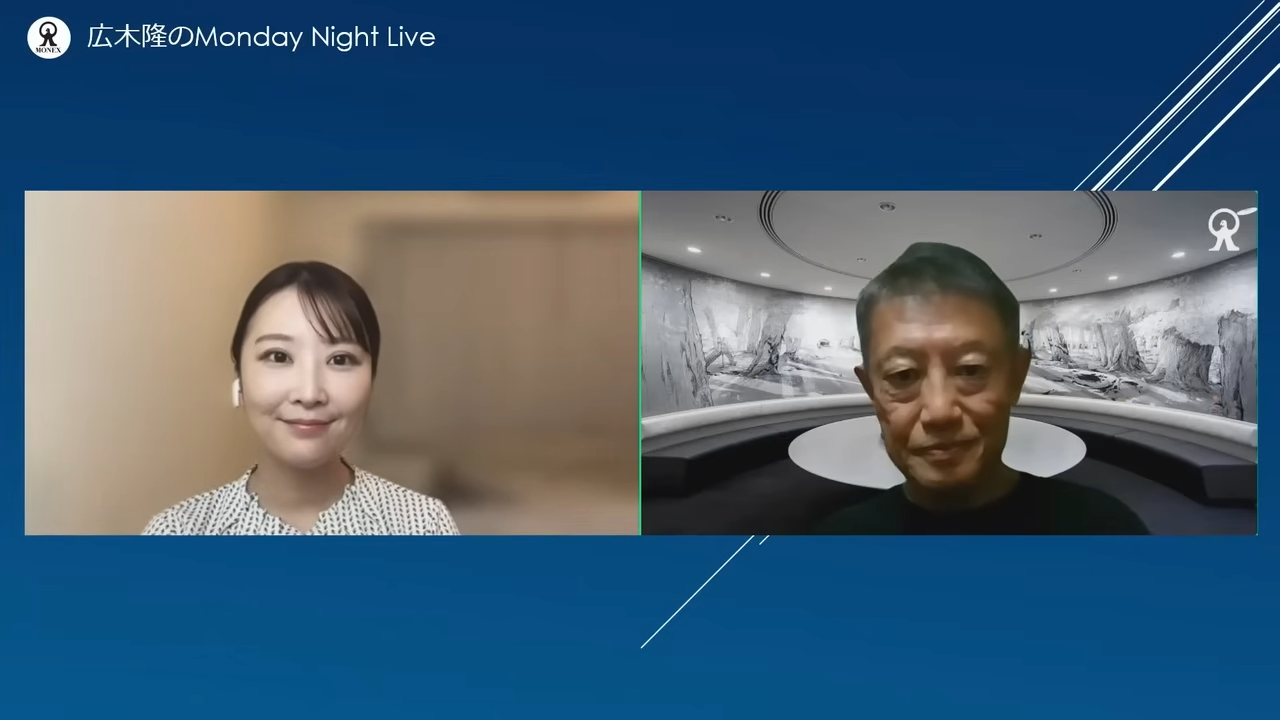
坂本:投資先という面でもう1つ、ご質問が来ています。「金の価格の今後について質問です。積み立て続けるのが良いでしょうか?」というご質問です。
広木:積み立てでやっているのであれば、それが一番良いと思います。金も結局、一本調子で上がってはいるものの、先週のように急落することもあります。
そもそも商品相場は値動きが荒いのが実情で、ここ最近のように安定して上昇していること自体はむしろ珍しいのです。コモディティの価格はファンダメンタルズではなく、需給だけで決まる特徴があります。
そのため、非常に値動きが激しく、いわゆる商品先物の世界では投機的な投資対象という位置付けです。特に日本の商品先物には小豆など、極めて日本独特のものもあります。いわば「山っ気」の強い、非常に投機性の高い市場です。
最近の金相場はまた別の世界ですが、安い時もあれば高い時もありますので、積み立てで買い続けるのは、非常に良い投資方法だと思います。
坂本:「東証の出来高と売買代金は、どの程度の水準が加熱レベルと言えるのでしょうか?」というご質問です。
広木:商いが盛り上がること自体は良いことで、加熱レベルというものは特にありません。当たり前ですが、売買代金はどちらか一方に偏ることはありません。買いがあれば必ずそれに見合う売りがあり、取引が成立します。
そのため「買い一辺倒」や「買いばっかりになっている」という認識は、非常に歪んでいます。結局、その買いに見合う売りが出てきて商いが成立しており、売り買いが釣り合っているということです。そう考えると、売買代金はいくら膨らんでも良いのではないかと僕は思います。
物色の対象となる銘柄について
坂本:「造船関連株が高騰していますが、今からでも買えますか?」というご質問です。
広木:大丈夫だと思います。今回の高市政権のテーマの1つにもなっていますし、日米の投資案件を考えた時に、「造船不足にまで手が回らないのでそこを何とかしよう」という動きがあります。「造船」という言葉はいろいろな意味を含みますが、テーマとしては注目しても良い分野だと思います。
坂本:日経平均のお話に戻ります。「『爆上げ』が怖いです。これはインフレの先取り、前ぶれではないかと思うのですが、今後どの程度インフレが進んでいくとお考えでしょうか?」というご質問です。「爆上げ」というのは、かなり上がっている、爆発的な上げということですね。
広木:「爆上げ」という感じはそんなにしないです。自民党総裁選が2025年10月4日の土曜日にあり、週明けに高市氏が選ばれ、日経平均は4万5,000円から一気に4万8,000円ほどまで上がりました。あれは確かに、1日の上昇率としては大きかったですが、その後は一気に飛び抜けている印象はあまりありません。
つまり我々の錯覚で、これまで「5万円」という水準は見たことないわけで、数字のインパクトが強いのです。例えば、今日も1,000円以上上がっていますが、5万円の水準で1,000円上がっても2パーセントなので、通常より少し強い相場であればそのような値動きはあり得ます。
少し前までは日経平均が2万円台で、400円、500円の上昇でもかなり大きく感じられましたが、現在は5万円ですから、1,000円の上昇でも2万円時代の400円、500円に相当する動きで、特別に大きく上がっているわけではありません。
大切なのは、足元の1日の大きな変動よりも、ここまで上がってきた経緯だと思います。今年は4万円割れの水準から始まり、春先にはトランプ関税の問題で大きく下げましたが、その後ここまで上がってきました。
値幅としては非常に大きいですが、年初の4万円弱から26パーセントほど上がっています。年間で2割、3割上がるというのは非常に大きな上昇率で、強い相場と言えます。
2023年の上昇率に比べれば、今年の上昇率は現時点で「極端に上がっている」状況ではないです。
「株価は上がるもの」という考え方
広木:これだけ良い条件が揃っている時に、株価が2割、3割上がるのはまったく不思議なことではありません。「爆上げだからどうこう」という話でもないです。
「株価が上がって怖い」「心配」という声に対して繰り返しお伝えしていますが、株価は上がっていくものです。上がるようにできています。2025年10月4日の「投資の日」に書いたレポートでも、そのメカニズムをご説明していますので、ぜひ読んでみてください。現在執筆中の書籍でも、くどいくらいに「なぜ株価が上がるのか」を盛り込んでいますので、そちらも読んでいただくとより腹落ちするかと思います。
もう心配なく株に投資して良いと思います。長期で持ち続ければ、結果的に資産運用は上手くいきます。なぜ上手くいかないかというと、「こんなに上がるのはおかしい」と怖くなって相場から降りてしまうためです。
あるいは、暴落や急落が起こると驚いて売ってしまいます。そうした経験から「上がり過ぎだ、売っておこう」と考えてしまうのです。結局のところ、「降りたら負け」なのです。
つまり、資産運用は継続し続ける必要があり、常にマーケットに居続けなければなりません。それができるのは、「株価は上がっていくものだ」ということに腹の底から納得できたときです。そうすれば、多少の上昇や下落があってもあわてて売ることはなく、運用をやめずにいられます。
そうしてマーケットに居続けることで、自然と長期投資になり、資産が複利で増えていく効果を実感できるようになります。そのためにも、「株価は上がるものだ」ということを腹の底から理解していただくことが重要です。
AI不況が日本経済に与える影響
坂本:続いて、AIに関する話題です。「日経平均を牽引している銘柄以外では、上げ下げしているものが多い気がします。AI不況はある日突然来るものなのでしょうか?」というご質問です。
広木:そんなことはありません。今でもすでに、じわじわと兆しが出てきています。先週末のレポートでも書きましたが、すぐに日経新聞でも同様の内容が報じられていました。米国の雇用環境が悪化し、就職が難しくなっているという内容のレポートです。ですから、そのようなAI関連の影響は現在進行形で見られ、統計データにも表れています。
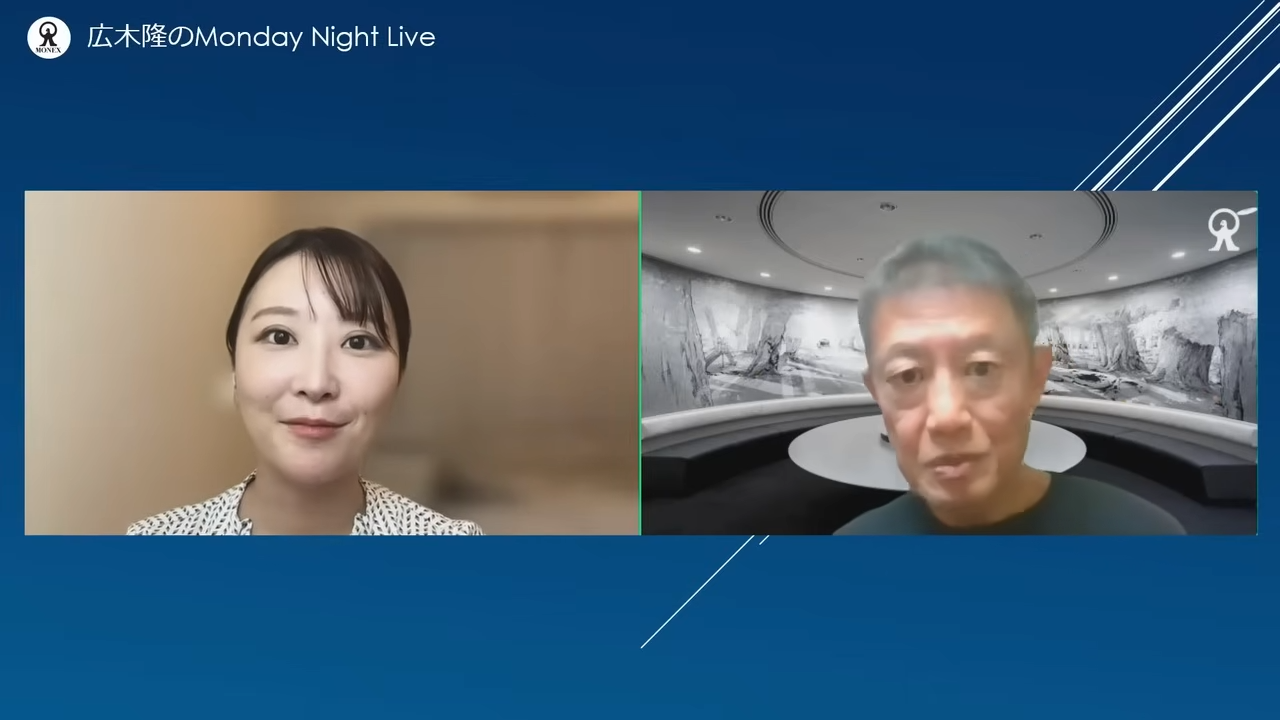
坂本:「電装株が徐々に上がってきましたが、自動車関連株は高市トレードに乗り遅れていた印象があります。ここに来て『出遅れ銘柄』として物色されているのでしょうか? まだ伸び代はありますか?」というご質問です。
広木:電装株、つまりデンソーを中心とする自動車電装部品メーカーは、もともと非常に良い銘柄群ですが、今回の高市トレードにおいては主役と呼べる位置づけではありません。
ただ、円安が進んだり、トランプ関税が落ち着いて全容が見えてきたりすれば、自動車に関する関税率などが明らかになり、業界全体の仕切り直しが起きる可能性があります。そうなれば、来期の業績見通しが見直され、メガサプライヤーの一角として再評価される可能性は十分にあります。そのような意味で、「出遅れ銘柄」として物色の手が入ってきやすいと言えます。
先ほどお話しした循環物色の流れの中では、非常に成長力のあるハイテク株だけではなく、バリュー株にも資金が回り始めています。そうした循環のなかで、電装株はコアな銘柄群として注目に値すると思います。
坂本:「防衛株が上がっていますが、特殊な商品なのに増産できるものなのでしょうか? もし、工場拡大のために新株を発行した場合、一気に値下がりする気もしますが、いかがでしょうか?」というご質問です。
広木:結局、増産のためにすぐに新たな設備投資が必要になるとは限りません。企業の意思決定としても、現時点で急いで設備を増強する必要があるわけではありません。
また、そのための資金調達の方法がエクイティファイナンスだけではありません。今はまだ金利水準が低く、今後の金利の先行きを考えれば借入による資金調達も十分に考えられます。
「防衛関連だからもっと増産しなければいけない」「では設備投資をしよう」「そのための資金調達をエクイティファイナンスで」という連想は行き過ぎています。まだその段階には至らないと思いますし、企業の増産体制にもいろいろな手段があると思います。一足飛びに「エクイティファイナンス=株価下落」と結びつけるのは早計のように思います。
坂本:「AI不況で日経平均はどうなるのでしょうか? 売られる銘柄、買われる銘柄も教えてください」というご質問です。
広木:AI不況の起き方についてご説明します。今すでに米国で起きていて、今後は米国景気の悪化をきっかけに波及してくると思われます。米国の景気が悪化するとFRBがますます利下げをして、米国のハイテク株が買われ、AIを手掛けているGAFAM等の銘柄はどんどん上昇します。したがって、当初の段階では株式市場全体が急落する事態にはなりにくいでしょう。
ただ、いずれ利下げを続けても景気が本格的に悪化した場合、看過できずに米国株が調整局面に入ると、日本株にも影響が及んできます。
日本の場合、最終的には米国のようなドラスティックなAI不況に行き着くと思いますが、そこに至るまでは時間がかかると思います。ようやく企業が「人的資本経営」を掲げ始めましたが、中身はまだ「人を大切にする」「人を育てる」という理念にとどまっています。これは、AIで若手を代替するという米国の動きとは真逆の発想です。
僕がレポートで引用した井上智洋氏の指摘ですが、日本ではAIが普及しつつある中で、むしろ若手を大切にする傾向が強まっています。人件費が比較的安い若手層を活用し、AIと人力を組み合わせるかたちで、結果的に中間層が圧迫されつつあるのが現状です。
いずれにせよ、AI不況が進めば、ホワイトカラーの職種がまず最初に影響を受けると思います。企業はかえって人件費を削減できる上、業務効率を高められるため、最初のうちはAIを積極的に活用します。AI不況になっても、割を食うのは一部の労働者層に限られます。
一方で、消費は伸びなくなります。日本の場合、AI不況でまず打撃を受けるのは、消費関連の分野ではないかと予想しています。百貨店や小売り業などは、インバウンド需要とどのようなバランスが取れるかはまだ予想ができません。
日本で本格的なAI不況が訪れるのはまだ先のことですが、長期的にはそうした変化を考えておく必要があると思います。
新着ログ
「証券、商品先物取引業」のログ





