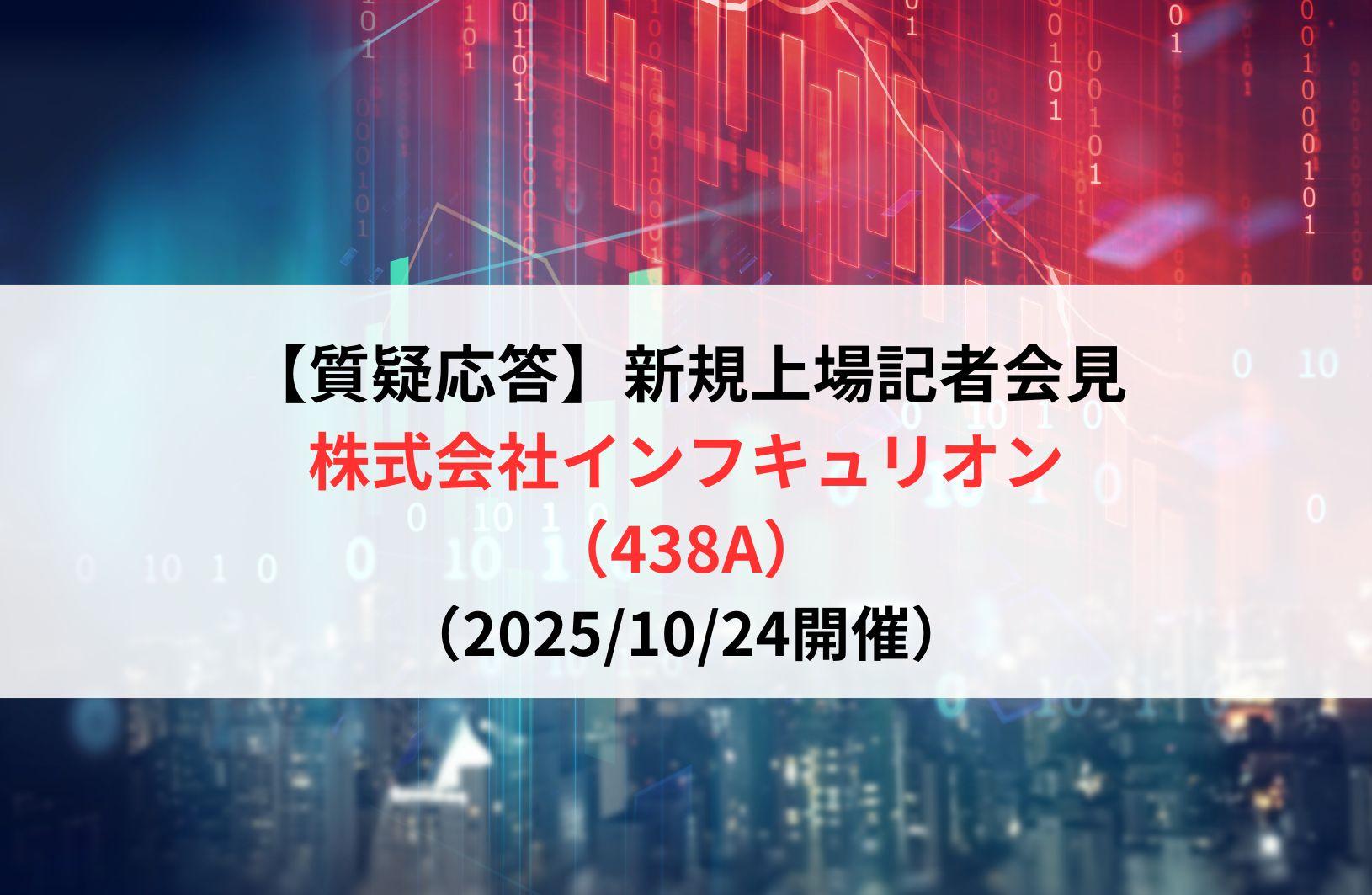株価チャートのパターンとは? 初心者が知っておきたい代表的な種類を紹介
株価のチャートパターンとは
ローソク足1本1本は、投資家の心理を表しています。そのローソク足がいくつも連なってできる「形」が、チャートパターンです。チャートパターンとは、株価の動きの中で繰り返し現れる特徴的な形を類型化したもので、投資家の心理や市場の勢いを読み取るために使われます。
チャートパターンを理解することで、上昇・下落の転換点やトレンドの継続を予測するのに役立ちます。テクニカル分析では、これらのパターンを「トレンド反転パターン」「トレンド継続(保ち合い)パターン」に分けて考えます。保ち合いは、「もちあい」と読みます。
株価チャートのパターン分析に使える3つの線
チャートパターンを分析する際に欠かせないのが、次の3つの線です。株価チャートに3本の線「トレンドライン」「サポートライン」「レジスタンスライン」を引くことで、チャートパターンが明確になり、売買タイミングの判断がしやすくなります。
トレンドラインは、株価の流れ(トレンド)を示す線です。上昇トレンドの時は安値同士を、下降トレンドの時は高値同士を結び、相場の傾き・勢いを表します。
例えば右肩上がりのトレンドラインを描けるうちは、相場の上昇基調が続いていると判断できます。株価がそのラインを下抜けた時にはトレンド転換のサインと見ることができます。

サポートライン(下値支持線)は、株価が下げ止まりやすい下値の壁を表す線です。過去に何度も反発した安値を水平に結ぶことで、その銘柄が「割安」と認識されやすい価格帯を可視化します。
株価がこのラインに近づくと、押し目買いが入りやすく、反発のきっかけになることが多いです。投資家心理でいえば、「この値段なら買ってもいい」という安心感が働くラインです。
レジスタンスライン(上値抵抗線)は、サポートラインの反対で、株価が上げ止まりやすい上値の壁を示します。過去に何度も反落した高値を水平に結ぶことで、投資家が「このあたりで利益確定しておこう」と考えやすい価格帯を表します。
株価がこのラインを突破できないうちは上値が重く、反落のリスクが高まりますが、逆に強い出来高を伴って突破すると、一気に上昇トレンドが加速することもあります。

株価チャートの代表的なパターン
株価チャートの代表的なパターンは、「トレンド反転パターン」と「トレンド継続パターン」の2つに分かれます。
トレンド反転パターンは、それまでのトレンドが終わり、新しいトレンドが始まる合図です。「ネックラインを終値で明確に抜けたら確定」というのが基本的な考え方です。
トレンド継続パターンは、株価エネルギーを充填する期間とも言えます。「上下どちらに抜けるか?」が勝負で、元のトレンド方向に抜けると続伸・続落しやすいとされます。
トレンド反転パターンとトレンド継続パターンを順に見ていきましょう。
反転パターン
ヘッド・アンド・ショルダー・トップ(三尊天井)/ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム(逆三尊)
ヘッド・アンド・ショルダー・トップ(三尊天井)やヘッド・アンド・ショルダー・ボトム(逆三尊)は、三つの山(または谷)が並ぶ形で、トレンドの転換点を示します。中央の山(または谷)が最も高い(低い)のが特徴で、「肩(ショルダー)・頭(ヘッド)・肩(ショルダー)」に見えます。
三尊天井は、上昇トレンドが終わり、下落へ転じる時に現れやすい形です。3つの山のうち、真ん中(頭)が最も高く、左右の山(肩)がほぼ同じ高さになるのが特徴です。
左肩部分では強い上昇(買いの勢い)が続いており、頭の部分では過去最高値をつけるが利益確定売りが出始め、右肩部分では再び上昇を試すが、前の高値を超えられません。そして終値がネックライン(左肩と右肩の谷を結んだ線)を割り込むと、下落転換のサインとなります。
逆三尊は、下落トレンドが終わり、上昇へ転じる時に現れる形です。三尊天井のさかさまの形です。左肩では下げ止まり一時反発するが、頭部分でさらに下落するものの出来高が減って売り圧力が弱まり、右肩で再び下げても前の安値を割りません。そして終値がネックラインを上抜けた時に、上昇転換のサインとなります。

ダブル・トップ/ダブル・ボトム
ダブル・トップ、ダブル・ボトムは、2回同じ水準で高値(または安値)をつけて反転するパターンです。まさにW(ダブル)の形になり、上昇相場が終わるサインや下落相場が終わるサインを見極めるのに役立ちます。どちらも「2回試してダメだった」あとに方向転換するという共通点があります。
ダブル・トップは、上昇トレンドが終わり、下落に転じる時に現れやすい形です。株価が高値をつけた後、一度下がり、再びほぼ同じ水準まで上昇します。しかし、2回目の上昇では前の高値を超えることができず、勢いが弱まったところで売りが増え、株価が下がり始めます。
投資家の心理としては、最初の高値では「まだ上がる」と強気で買いが入ります。ところが、2回目の高値を超えられないことで「もう天井かもしれない」という不安が広がり、利益確定の売りが出てきます。そして、2つの山の間にある谷を通るネックラインを株価が下回ると、「いよいよ下落トレンド入りだ」と多くの投資家が意識し、本格的な下げ相場へと移行します。
ダブル・ボトムはその逆で、下落トレンドが終わり、上昇に転じる時に現れます。株価が下落して安値をつけた後、一度反発しますが、再び同じような水準まで下がります。しかし2回目の下げでも前の安値を割り込まず、そこから上昇に転じていく。つまり、「もうこれ以上は下がらない」という市場の安心感が生まれる場面です。
投資家心理的には、最初の安値で多くの投資家が悲観して売りを出します。少し反発しても「また下がるだろう」と考えて再び売りが出ますが、2回目の下げで安値を更新できなかったことで、「売りの勢いが弱まってきた」と感じた投資家が買いに転じます。そして2つの谷の間にある高値(ネックライン)を上抜けると、上昇トレンドへの転換が意識され、買いがさらに加速していきます。

トリプル・トップ/トリプル・ボトム
トリプル・トップ、トリプル・ボトムは、先ほど説明した「ダブル・トップ/ダブル・ボトム」ととても似ています。違いは「2回ではなく3回」同じ水準を試す点です。それだけに、その水準が強い壁であり、反転の信頼性がより高いパターンとして知られています。
トリプル・トップは上昇相場の終盤で見られる形です。株価が上がっていき、ある水準でいったん止まります。その後もう一度、そしてさらにもう一度と、合計3回ほぼ同じ高値をつけるものの、いずれも前回の高値を超えることができません。まるで「3回天井を叩いても抜けなかった」形で、買いの勢いが次第に弱まっていることを示します。
最終的に3つの山の谷を結んだネックラインを下抜けると、それまでの上昇トレンドが終わり、下落トレンドへ転換したと判断されます。
トリプル・ボトムはその逆のパターンです。下落相場の終盤で、株価が安値をつけるものの、その後3回連続でほぼ同じ水準で下げ止まる形を描きます。何度も下を試しても割れない、つまり「底堅い」ことを示しており、ネックラインを上抜けると上昇トレンドへの転換が強く意識されます。
トリプル・トップ、トリプル・ボトムは、「3回試しても超えられなかった(下回らなかった)」ことを示す強い反転パターンです。ダブルよりも形成に時間がかかるぶん、相場のエネルギーがしっかり蓄えられており、ブレイク後の値動きが力強くなる傾向があります。そのため、中長期のチャート分析でこれらのパターンが現れると、投資家たちは「いよいよ転換かもしれない」と注目します。

ソーサー・トップ/ソーサー・ボトム
ソーサー・トップとソーサー・ボトムは、名前のとおり、まるでお皿(ソーサー)のようにゆるやかなカーブを描いて反転するパターンです。鋭く反転する「ダブル・トップ」や「三尊天井」とは違い、時間をかけてじっくりとトレンドが変わるのが特徴です。そのため、長期的なトレンド転換を示すサインとして注目されることが多く、日足よりも週足や月足など、長めのスパンで確認されることが多いパターンです。
ソーサー・トップは、上昇トレンドが続いた後に現れ、ゆっくりと天井を形成して下落へ転じるパターンです。形としては、株価が少しずつ上げ止まり、高値を更新できなくなりながらゆるやかに山型のカーブを描くように見えます。
これは、投資家心理が「強気から中立、そして弱気へ」と徐々に移り変わる過程を表しています。上昇相場が長く続くと、最初のうちは「まだ上がる」と買いが入りますが、次第に利益確定売りが増えて勢いが弱まり、最終的には「もう上がりきった」と感じる投資家が増えて売りが優勢になります。
特徴的なのは、急激に崩れるのではなく、時間をかけてじわじわと下がり始める点です。そのため、途中では「横ばいに見える時期」が長く続くこともあります。この横ばいを抜けて下方向に動き出した時、「トレンド転換が明確になった」と判断されます。
ソーサー・ボトムは、下落相場の終盤に現れるパターンです。株価が長く下げ続けたあと下げ止まり、ゆるやかなU字型(お皿型)を描いて反発に転じます。
これは、投資家の心理が「弱気から中立、そして強気へ」と変化していく様子を表しています。下げ相場が長く続いたあと、最初のうちはまだ売り圧力が強いですが、少しずつ「このあたりが底かもしれない」と考える人が増え、売りが減って出来高も落ち着きます。その後、反発が始まり、直近高値を明確に超えたところで上昇トレンドに転換したと考えられます。
ソーサー・ボトムも、急上昇するというよりは、時間をかけて底固めをした後に反発する形が多く、長期投資家にとっては「買いの好機」とされる局面になります。
どちらも「時間をかけて相場の雰囲気が変わる」ことを示すパターンです。短期トレードよりも数ヶ月〜数年単位でのトレンド分析に向いており、例えば業績改善や景気循環など、ファンダメンタルな変化と相性が良い点が特徴です。

保ち合い(継続)パターン
三角保ち合い
三角保ち合い(さんかくもちあい)は、株価が上昇と下落を繰り返しながらも、その値動きの幅(高値と安値の差)が次第に小さくなり、チャート上で三角形のように収束していくパターンを指します。これは、売りと買いの力が拮抗している状態を表しており、最終的にはどちらかの方向へ大きく動く「ブレイク」が起こるのが特徴です。高値が切り下がり、安値が切り上がっていくことで、チャートが三角形のように収束していきます。
三角保ち合いの背景には、投資家の心理的な迷いがあります。相場が一方向に大きく動いたあと、「これ以上上がらないのでは」「もう下げ止まったのでは」と考える投資家が増え、売りと買いが均衡します。その結果、値動きがだんだんと小さくなり、高値は切り下がり、安値は切り上がっていく。こうしてチャート上に三角形が現れます。
三角保ち合いにはいくつかのタイプがあります。対称型三角保ち合いは、高値が少しずつ下がり、安値が少しずつ上がっていくタイプです。上下どちらにブレイクするかで、その後のトレンドが決まることが多いです。上方向に抜ければ上昇トレンド、下方向に抜ければ下落トレンドが加速する可能性が高まります。
上昇型三角保ち合いは、上値がほぼ水平で下値が切り上がる形です。買い圧力が強まっており、レジスタンスラインを抜けると一気に上昇するケースが多いです。
下降型三角保ち合いは、下値がほぼ水平で、上値が切り下がる形です。売り圧力が優勢で、サポートラインを割ると急落することがあります。
投資家心理の流れとしては、三角保ち合いの中では「どちらに動くかわからない」という様子見のムードが強まります。出来高(取引量)も次第に減少し、市場のエネルギーがため込まれていきます。そして、ある瞬間にどちらかのライン(上限または下限)を明確に抜けた時、エネルギーが一気に放出され、新たなトレンドが生まれます。

ペナント型
ペナント型は、相場の途中で一時的に小さく保ち合う形のことです。チャートの形が旗の先につく三角形の「ペナント(旗じるし)」に似ているため、この名前がついています。
ペナントは、強いトレンドの途中に現れる一時休憩のようなもので、上昇トレンドの中に出れば「上昇ペナント」、下落トレンドの中に出れば「下降ペナント」と呼ばれます。
例えば、株価が勢いよく上昇した後、短期間のうちに小さな値幅で上下を繰り返しながら三角形を作ることがあります。これは前の急上昇で一度利益確定の売りが出て、同時に「押し目を待つ買い」も入ってくるため、売りと買いが一時的に拮抗している状態です。この時のチャートをよく見ると、高値が少しずつ切り下がり、安値が少しずつ切り上がっていく形、つまり小さな対称型三角形(ペナント)ができています。
投資家心理で見れば、ペナントの中では「一度利益を確定したい人」と「押し目で買いたい人」または「戻りで売りたい人」とがぶつかって、売りと買いが均衡しています。しかし時間が経つにつれて、その均衡が崩れ、どちらかの勢力が勝った時に、一気にトレンドが再開します。このブレイクが起きる瞬間は、出来高が増えるのも特徴です。
三角保ち合いはトレンドが落ち着いた後に出てくることが多く、「上にいくか、下にいくか、まだ決めかねている」状態を表します。一方のペナント型は、強いトレンドの途中で現れるのが大きな違いです。上昇中なら「上昇ペナント」、下落中なら「下降ペナント」と呼ばれます。
急激に動いたあとの短い期間に、値幅が徐々に狭まっていく形で、やはりチャート上は小さな三角形になります。ただし、ここでは相場が休憩しているだけなので、エネルギーがたまったあとに元のトレンド方向に再び動き出すことが多いのです。
ボックス型
ボックス型は、株価がある一定の範囲の中で上下に行ったり来たりを繰り返すパターンです。ボックス相場といわれることもあります。チャートで見ると、上値のレジスタンスラインと下値のサポートラインの間を、株価がまるで箱(ボックス)の中で動いているように見えることから、こう呼ばれます。
ボックス型では、相場の方向感が定まっていません。上にも下にも抜けきらず、売りと買いの力がちょうど釣り合っているのです。「上がれば売られ、下がれば買われる」という力が働くため、価格は一定の範囲で何度も反発や反落を繰り返します。
投資家心理で言えば、ボックスの上限(レジスタンスライン)付近では、「前回ここで下がったから、今回も売っておこう」という売りが出やすくなり、逆に下限(サポートライン)付近では、「このあたりで反発するだろう」という買いが入りやすくなります。こうした心理の繰り返しが、ボックス相場を形成していくのです。
ボックス相場は動かない退屈な相場ですが、見方を変えればトレンドが次に動き出す前のエネルギー蓄積期間とも言えます。長く続いたボックスの中で出来高が減少し、値動きが小さくなってくるのは、市場のエネルギーが蓄積されている状態です。その後、どちらか一方にブレイクした時には、強いトレンドが発生することが多いのです。

フラッグ型
フラッグ型は、株価が大きく上昇または下落したあとに、一時的な調整を挟んで四角い旗のような形を作るパターンです。その名のとおり、強いトレンドのあとに短期間の休憩が入る形が旗(フラッグ)に似ているため、この名前で呼ばれます。
投資家心理で見れば、フラッグの中では「一息入れたい」ムードが強まっています。急騰・急落のあとの短い調整期間で、売りと買いのバランスが一時的に取れている状態です。しかしトレンドの勢い自体はまだ終わっていないため、ブレイクした瞬間には出来高を伴って再び大きな動きが出るのが特徴です。

反転・保ち合い(継続)両方の意味持つパターン
ウェッジ型
ウェッジ型は、株価の高値と安値がだんだんと近づいていくように斜めに収束するパターンです。見た目は三角保ち合いに少し似ていますが、三角保ち合いが「横向き」に収束していくのに対し、ウェッジ型は斜めに傾いた三角形を描くのが特徴です。
上昇ウェッジは下落転換のサイン、下降ウェッジは上昇転換のサインになることが多いですが、トレンドの途中で現れることもあり、反転・継続どちらにもなりうる点が特徴です。ポイントは、どちらにブレイクするか。トレンドラインを抜けた方向が、その後の動きを決定づけることになります。
上昇ウェッジは、株価が上昇している最中に現れるパターンで、高値と安値の両方が少しずつ切り上がりながら、くさびのように収束していく形をしています。見た目は右肩上がりの小さな三角形です。いかにも「上昇トレンド継続」に見えるのですが、実際には買いの勢いが徐々に弱まり、反転下落のサインになることが多いです。
投資家心理で言えば、最初は強気の買いが続いていますが、だんだんと「高値でもう買えない」と感じる人が増え、出来高も減って勢いがなくなっていきます。そして、サポートラインを割り込むと、「上昇トレンドが終わった」と見なされ、売りが加速する傾向があります。

YouTube「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」
著書「世界一やさしいファンダメンタル株投資バイブル」
公認会計士の個人投資家。京都大学を卒業後、2003年、監査法人トーマツに入所、世界的な上場企業を担当する。2007年、独立。公認会計士事務所を開業。一方でアクションラーニング社を立ち上げる。同社では初心者投資家向けに、決算書をいかに株式投資に活用するかを中心に講義を行い、多くの個人投資家に実践的な知識を提供。「どんなに難しいことも、わかりやすく」の授業コンセプトは絶大な支持を得る。投資スタイルは、「決算書・IRなどから良い企業を見抜き、安く買って、持ち続ける」というファンダメンタルズ分析に基づく長期投資。