kenmo氏がIRセミナー活用法を徹底解説! 投資家目線で注目すべきポイントと質問術
IRセミナー徹底攻略!セミナーを読み解くhow to 伝授#3
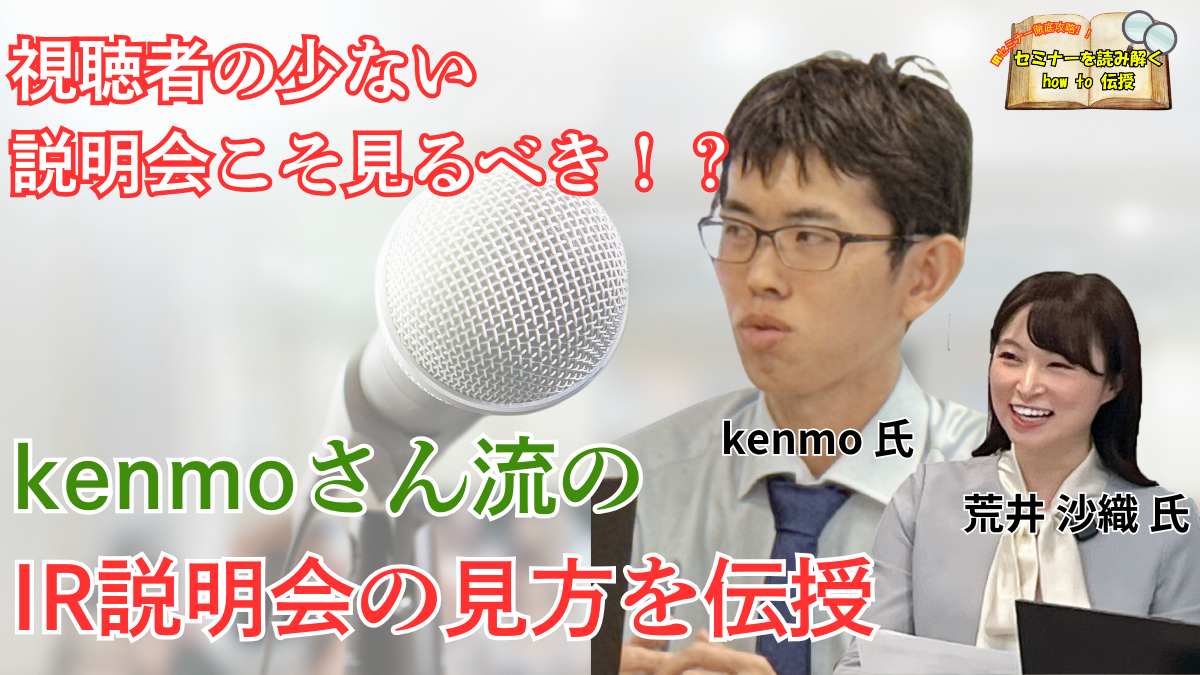
荒井沙織氏(以下、荒井):みなさま、こんにちは。荒井沙織です。この動画では、ふだんIR説明会をあまり見ない方や、見てもどのように投資判断に使えばいいのかわからないという方に、実際のIR説明会の映像を一緒に見ながら、どこに注目すべきか、どのように活用すればいいかを凄腕投資家が丁寧に解説していきます。
今回のゲストはkenmoさんです。よろしくお願いします。
kenmo氏(以下、kenmo):よろしくお願いします。
荒井:みなさま、もちろんご存じかとは思いますが、あらためて自己紹介をお願いします。
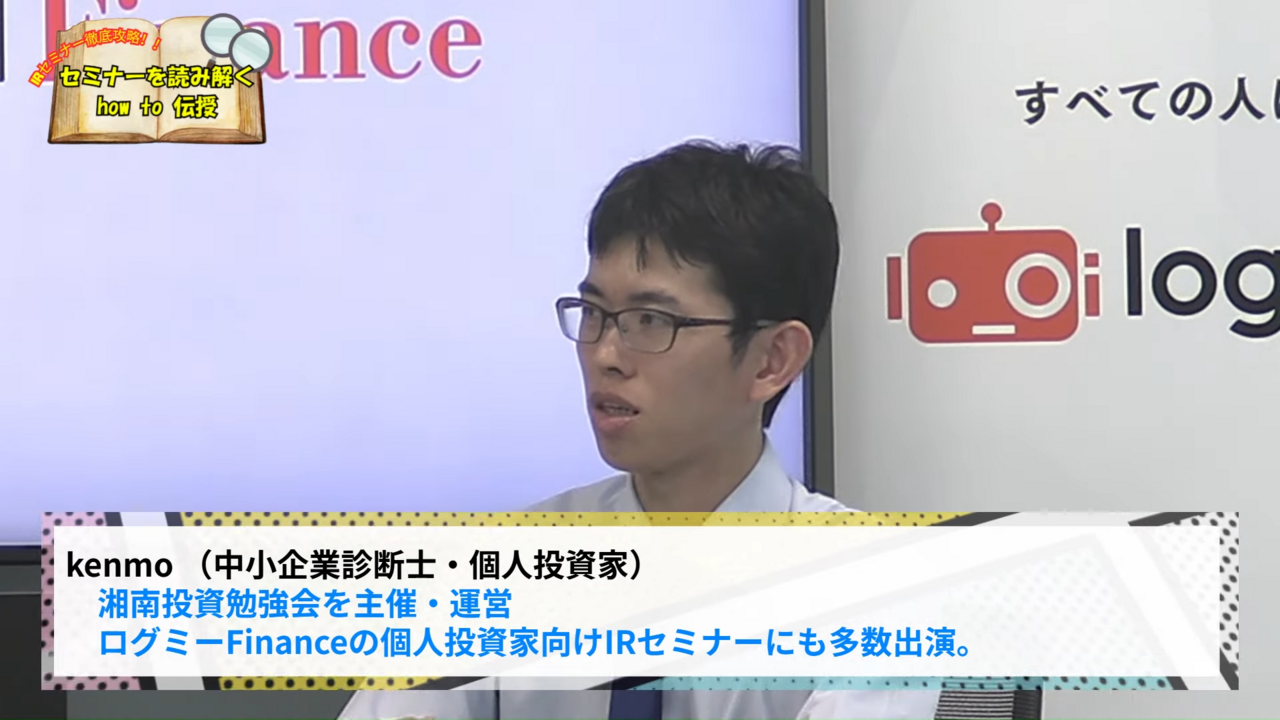
kenmo:kenmoといいます。敏腕投資家といわれると恥ずかしいですが、よろしくお願いします。ログミーFinanceでファシリテーターを担当しているほか、「湘南投資勉強会」という勉強会やIR説明会の運営などを行っています。
また、2025年4月23日に『5年で1億貯める株式投資』という書籍を出版しました。実際のところ、これほどまでに売れてしまっていいのかと思っています。
荒井:発売されてから、瞬く間に増刷を重ねていて、本当にすばらしいです。
kenmo:12万部を達成しました。手に取っていただき、本当にありがとうございます!
荒井:おめでとうございます! 「この時代に、こんなに本が売れるなんて」という感じですね。
kenmo:「本当にありがとうございます」というところです。
荒井:この表紙のタイトルを見ただけでも、kenmoさんが敏腕・凄腕なのは確定ですね。この書籍の中にある要素も、少し教えていただけるのでしょうか?
kenmo:そうですね。書籍にある要素のほか、書かれていない要素もお話しします。
荒井:たっぷりとお話をうかがっていきます。よろしくお願いします。それでは、始めましょう。
IR説明会の活用方法
今回は、IR説明会の活用方法についてお話しいただきます。kenmoさんは、数々のIR説明会を主宰しているほか、参加もされていると思います。kenmoさん流の活用法をぜひ教えてください。
kenmo:「IRセミナー徹底攻略!セミナーを読み解くhow to 伝授」は、前回、前々回はKenさんが出演されて、私が2人目です。Kenさんは本当にすばらしい投資家なので、動画を見ていただければすべてわかるところではありますが、僭越ながら、私なりの考えをお話しします。
荒井:はい。kenmoさん流でお願いします。
kenmo:一般的にIR説明会は、「企業理解を深めましょう」とか「その会社の投資判断に役立てましょう」というのが、いわゆる表向きの活用法ですが、正直、会社が「儲けるため」のものです。株で儲けるために活用するのが、IR説明会です。会社としては、自社の株を買ってほしいという思いがあります。
一方で、投資家の立場としては、その会社の株を買うかどうかよりも、むしろ自分が儲けるために活用するのがIR説明会です。したがって、そこは割り切ってしまっていいと思います。
荒井:儲けたいです(笑)。では具体的に、IR説明会をどのように活用していったらいいのかを教えてください。
kenmo:ちなみに荒井さんは、IR説明会を見て「ちょっと、この会社いいな」と思ったり、実際に株を買ってみたりしたことはありますか?

荒井:あります。ただ、私はIR説明会を聞いて、社長やIR担当の方の熱意に心をグッとつかまれてしまうタイプなので、気をつけなければいけないとは思っています。熱に押されがちです(笑)。
kenmo:それは、7割は正解ですが、3割は気をつけなければなりません。
IR説明会の一番いい点は、社長の生の声がダイレクトに聞けるところだと思います。基本的に、決算説明資料は数字の話やビジネスモデルの話が多いですが、どのような社長が引っ張っているのかということを、実際に動画を見て、社長の話を聞きながら、身振り手振りなども含めて判断することが非常に大事です。
一方で、荒井さんのおっしゃるとおり、基本的に上場会社の社長は、特に創業社長はエネルギッシュで魅力的です。カリスマ性にあふれており、非常にやる気を持って説明してくださいます。なので、「この会社、いいな」とか「社長、ちょっとかっこいいな」と感じて投資判断をしてしまいがちですが、基本的に社長はそのようなものだと割り引いて考える必要があります。
その上で、やはりいいなと思う会社であれば、まずはウォッチリストに入れて、業績を確認してから、いいところで買うことが大事かと思います。
荒井:今のところ、担当してお話をうかがった会社は全部リストに入っているのですが(笑)、どのように振り分けていけばいいかを教えてください。
知らなかった会社を知ることができる
kenmo:IR説明会は、活用方法が2つあると思っています。1つ目の活用方法は、銘柄の発掘です。IR説明会を見て、「この会社、いいな」とか「こんなビジネスモデルの会社があるんだ」など、今まで知らなかった会社を知ることです。
しかし、「この会社、いいな」と思ったからといって、すぐに「買い」のボタンを押すべきではありません。その会社の変化するタイミングや、いい決算を出したタイミングなどのほかに、全体的に相場が軟調になった時に、「あの時、IR説明会で見た会社を見てみよう」というかたちで入るのがベストです。
例えば、「いい決算を出した」、あとは「相場がクラッシュした」などの時に、いち早く「そういえば、IR説明会で見たあの会社」と思い出して、すぐに「買い」のボタンを押しにいけるかが大事です。
タイミングを逃さず素早く「買い」を入れる
2つ目の活用方法は、「この会社、いいな」と思ったら、まずはウォッチリストに入れ、そのあとに良い決算や材料が出た時や、全体の相場がクラッシュしてその会社の株価がグッと下がった時に、素早く「買い」を入れられるようになることです。
荒井:一目惚れだけではダメなのですね。そのあともきちんと追いかけて、いいタイミングを狙います。
kenmo:したがって、荒井さんは、ウォッチリストに入れるところまでは大正解なのです。
荒井:もう、一目惚れだらけですね。
kenmo:そこから、どのようなタイミングでどの株を買うかというところですよね。
荒井:そこがもう、いっぱいいっぱいになっていますが(笑)、「特にこの会社を見ていきたい」というポイントになる要素として、IR説明会で会社に質問をできる点が大きいと思います。
質問といっても、何を聞いたらいいかわからないという方や、「このような質問をしたら失礼かな」とか「怖いな」と思っている方も多いかと思いますが、質問をする上でのポイントはありますか?
質問時のポイント
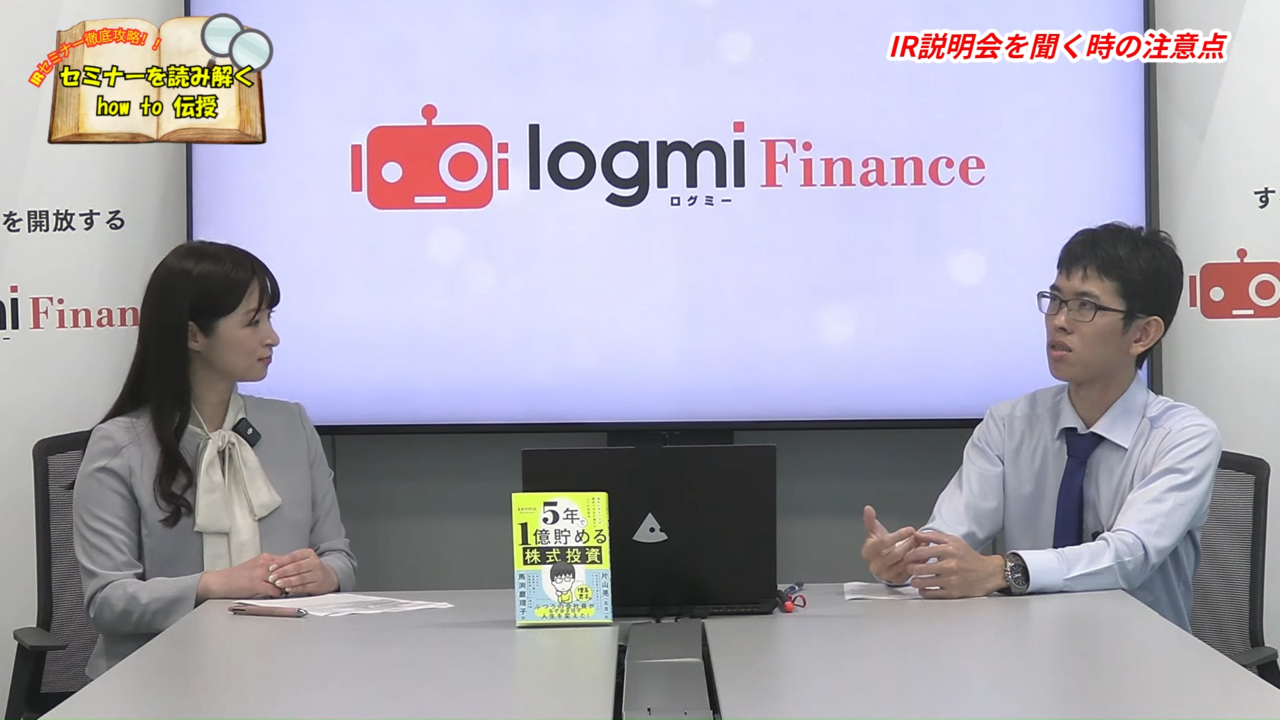
kenmo:「なんでもいい」というのが結論です。特に、ログミーFinanceは匿名で質問できるので、「このような質問をしたら恥ずかしいかな」とか、「このような基本的な質問をしたらいけないかな」などは、まったく気にする必要がありません。
したがって、「優待を出しませんか?」や「配当方針を教えてください」という質問でもいいと思います。場合によっては、「社長の趣味は?」という質問なども採用されることがあります。
自分が気になったことであれば、本当になんでもいいのです。ただ、最初に言ったとおり、IR説明会は自分が儲けるために聞くものだと思うので、やはり「儲けるために、何を聞けばいいのか」というところがポイントです。
いろいろありますが、私が一番よくする質問は、人材や組織についてです。具体的には、採用や教育、組織に関するところですね。
荒井:それは、何のために聞くのですか?
kenmo:社長や説明資料を作る方など、その会社で働いている人たちは、毎日通勤して、毎日顔を合わせているため、どのような環境で働いているかをあえて資料に書くという考えに至らないケースがあります。
しかし、投資家側からすると、実際にオフィスに行くことができないため、どのような人たちが、どのような顔をして、どのようなところで働いているのかというところは、まったく見えません。
会社というのは人によって動いています。つまり、人がいないと回らないため、どのくらいの人が、どのようなところで、どのような気持ちで働いているのかというところが、投資判断には非常に大事なのです。
嫌々働いて売上・利益を作っているのか、それとも、社員が非常にモチベーションを高く持って働いて売上・利益を作っているのかが見えれば、「このような社員や組織であれば、おそらく今期の売上利益だけでなく、来期・再来期も作っていけそうだな」というところに思い至るわけです。
会社側は、当たり前に接している部分があるため、書くというところまでに至らなくなるのです。
荒井:会社側は、人材や組織について知ることが、投資判断に必要とされているとは思っていないということですね。
kenmo:はい。そこで「ここが知りたいです」と質問を投げかけると、会社によっては、「今まで採用の数などは開示していなかったけれど、そういう質問をいただいたので、あるタイミングから開示するようにしました」と、次回の決算説明資料で改善してくれたり、実際に答えてくれたりすることがあります。そのため、私は人材や組織について聞くようにしています。
加えて、社長の目線についても質問します。具体的には今後の成長戦略についてですが、成長戦略という抽象的な聞き方をしてしまうと、社長の回答も抽象的になってしまいます。したがって、もう少し答えやすいように、自分の仮説を質問の中に入れたりすることもあります。
質問に自分の仮説を織り交ぜる
例えば、「私はこの市場環境をこのように見ていますが、社長はどう見ていて、今後どういう成長戦略を打っていきますか?」と質問すると、その仮説が合っている場合は「合っています」と答えてくれるし、仮に間違っていても、「間違っています」と訂正した上で自分の話をしてくれます。
仮説をぶつけると、それが合っているのか間違っているのかを判断した上で回答がもらえるため、仮説を質問に入れてみるのは大事です。
荒井:仮説を組み立てている段階で、質問者の方がその会社や業界にしっかり向き合っているという姿勢も伝わりそうです。
kenmo:そうですね。私がよく使うコツとして、例えば「同業他社のIR説明会ではこのように言っていましたが、御社はどうですか?」という聞き方です。回答によってはもしかしたら、「この会社よりも、この間の会社のほうが良かった」というような比較検討もできるのでおすすめです。
荒井:会社としては、突かれたくないところを聞かれる場合もありそうです。
kenmo:そうですね。社長も人間なので、質問の内容によっては答え方が曖昧になったり、あるいは、強い自信を持った答え方になったりします。
ただし、自信を持った答え方によって、「ここに対しては自信があるのだな」と判断するのも正しいのですが、場合によっては「こう聞かれたら、とりあえずこのように答えておこう」というような想定問答である、会社にとっての定番質問にはまったケースもあります。そこに関しては、見極めるコツが必要なところです。
社長が本当にそう思って言っているのか、それとも「とりあえず、こう聞かれたらこう答えよう」という定番質問に対するテンプレート的な回答なのか、そこを見極めるのがコツであり、IR説明会のおもしろいところかと思います。
荒井:目を見てというか、表情をしっかり見ながら聞けるのが、やはりポイントですね。
kenmo:そうです。IR説明会の場では、社長からインサイダー情報を話すことは絶対にできません。どうしても「ここまでは言いたい」というところまで言ってしまうとインサイダー情報になるため、だいたいはもう一歩手前で止めるのです。「本当は話してもいいけれど、インサイダー情報としてグレーのラインなため、ここまでにしておこう」と、当たり障りのない回答で終わってしまうケースがあります。
そのようなケースでは、ギリギリのところを聞きたいので、「もう少し具体的に教えてください」や、「とは言うものの」のように聞き直してみると、会社ももう少しギリギリのところを答えてくれます。
ある質問の回答に対して、追加で「さらにここが気になった」や、「もう少し詳しく、ここまではなんとか教えてください」というように聞き出すのがポイントです。
IR説明会を聞く上での注意点
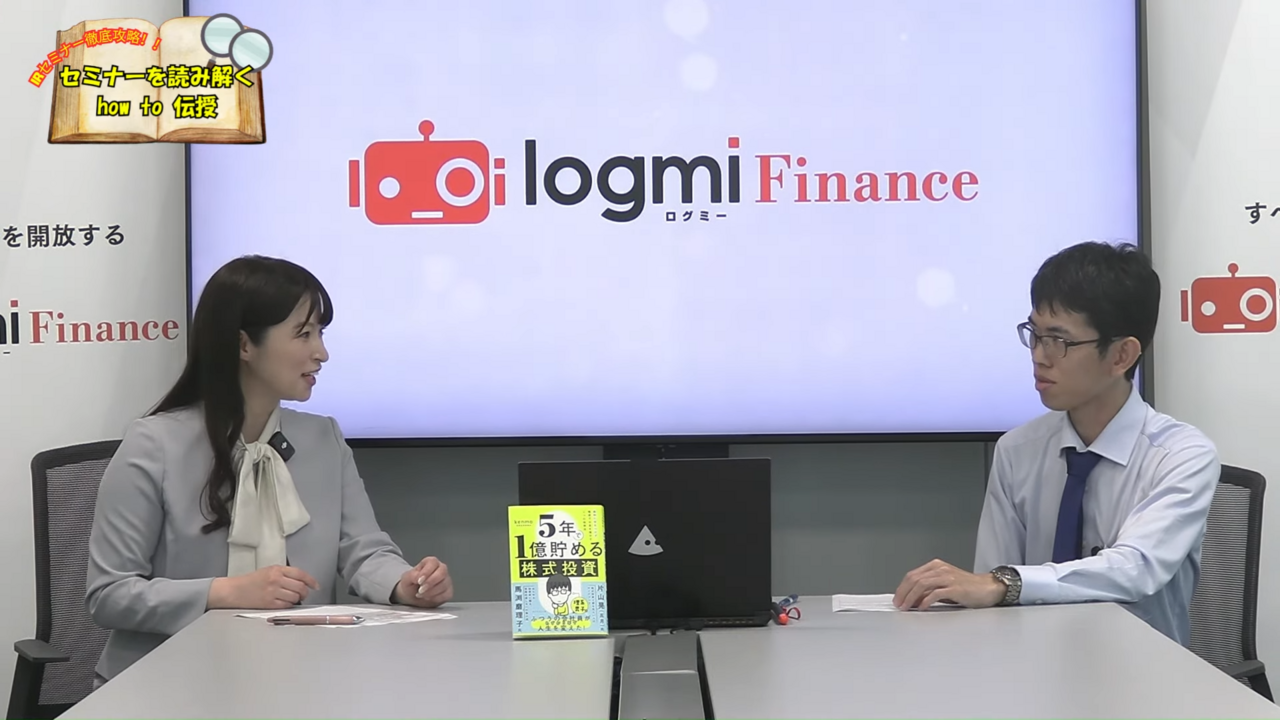
荒井:それでは、最初のほうでも少しお話はありましたが、IR説明会を聞く上での注意点も教えてください。
kenmo:いくつかあります。まず、先ほども少し触れたとおり、会社としては「自社に興味を持ってもらいたい」「自社の株式を買ってもらいたい」という思いでIR説明会に登壇されます。また、IR説明会にあまり登壇したことのない会社の場合、どこまで話していいかわからないため、当たり障りのない回答で終始してしまうところがあります。
そのような中で、会社にとって良いことだけを話す場合もあります。あるいは、あまりに不慣れであるがゆえに、本当はもっと話していいのに、当たり障りのない内容で終始するIR説明会もあります。そのような会社の説明内容と、投資家の知りたいこととのギャップを埋めるのが質疑応答だと思っています。
IR説明会は、あくまでも会社がまず話したいことを話す場なので、それを受けて投資家側として知りたいことを質問することが非常に大事です。社長の説明だけを聞いて「なるほど、そのような会社なのか」と思うのではなく、質問してより正確な情報の、裏を取っていくのが重要だと思います。
視聴者数が少ないIR説明会の魅力

また、会社の認知度や注目度で差が出るのは仕方のないことですが、多くの視聴者がいて多くの質問が出るIR説明会と、まったく人が来ず質問も少ないIR説明会があります。しかし、意外と誰も見ていない、質問も少ないIR説明会のような、市場からもいまだ注目度を集めていないところに、掘り出し物やお宝が眠っているケースもあります。
「みんなが見ていて視聴率も高いのだから、この会社は良い」というのも、それはそれで正しいのですが、他の投資家がすでにその会社の良さを知っていて株を持っていると考えると、非常に割高に評価されている場合があります。一方で、注目されていない会社は割安に評価されている場合があります。そのような掘り出し物を見つけられるのも、IR説明会の醍醐味かと思います。
荒井:なるほど。そのような視点は持ったことがありませんでした。今は本当にIR説明会がたくさんあるため、すべてを見ることは不可能です。例えばYouTubeにアーカイブが残っている中で、再生回数が少ないものから見てみるというのはありですか?
kenmo:それはいいかもしれません。私は、IR説明会は最初から最後まで見なくていいと思っています。それこそ説明開始から2分、3分で「この会社はいいや」と思ったら、もう見なくていいと思います。
約3,900社の全上場企業の中で、自分自身が買う銘柄はほとんどの人はせいぜい数十社程度、人によっては100社か200社程度だと思います。組み入れない銘柄のほうが大多数なわけです。したがって、最初の2分、3分程度を見て、「この会社は投資対象にならない」と思えば次の動画に行っていいと思います。
荒井:kenmoさんはどのようなところを見て「この会社はスキップしてしまおう」と思うのですか?
kenmo:第一声というか、最初のスライドが大事だと思うことがあります。
荒井:会社の沿革や、パーパスといった部分ですよね。
kenmo:そうですね。やはり、サラリーマン社長よりも創業社長のほうが、自分の言葉で話をします。最近は資本コストと株価を意識した経営の話があり、いわゆるサラリーマン社長が経営するオールドエコノミーのような会社や、比較的PBRが低い昔ながらの会社のほうが還元を強化する動きがあるため、株価が堅調ではあります。
とはいうものの、業績やEPSを伸ばしていくという観点では、創業社長が自分の言葉で発信する会社のほうが、その意欲は強いと思います。サラリーマン社長でも2代目や3代目の交代のタイミングや、業績が少し軟調になったタイミングでテコ入れのために経営陣を刷新するような、「ここからやる気を出していくぞ」というケースがあります。
したがって、サラリーマン社長でもいいのですが、最初の1枚目、2枚目のスライドの入りや、それを自分の言葉で発信しているかどうかを感じ取ることが大事だと思います。
荒井:確かに、その時の熱量が、後半の質疑応答の熱量にも反映されている可能性がありますね。おもしろいです。
kenmo:そうですね。説明を社長が行う会社は、当然、質疑応答も社長の言葉で回答していただけるので、そこはまず見ます。ただし、社長が前のめりしすぎる会社も、私は「ちょっと待って、そこまで来なくていい」と思うことはあります。
荒井:kenmoさんのポイントを、なんとなく肌感覚で受け取れたかと思います。
書き起こしを活用して情報収集

kenmo:もう1点、私は動画よりも書き起こしを見ます。ログミーFinanceは書き起こしが非常に充実していてすばらしいと思います。
ログミーFinanceのすごいところは、自社で行ったIR説明会だけではなく、各会社の決算説明会や別のところの説明会も書き起こしが上がっているところです。これが非常に役に立っています。書き起こしを読んで気になる会社があれば、「どういう方が話をしているのだろう」と動画を見て、さらに深掘りしていくことも非常に多いです。
荒井:なるほど。魅力的な会社を発見する方法は、いろいろありますね。
kenmo:そうですね。この説明会をご覧の方も、ふだん仕事で忙しい方だと思いますので、可能な限り時短でいい銘柄・いい会社を発掘していただけるといいなと思います。
荒井:みなさま、いかがでしたでしょうか? kenmoさんのIR説明会に対する目線の持ち方などをご説明いただきました。冒頭の1枚目、2枚目のスライドが、この後も聞く価値があるかどうかの大きな判断基準になるという点もおもしろかったです。
次回は、kenmoさんが実際に聞いてよかったと思うセミナーをご紹介いただきます。それではみなさま、次回をお楽しみに!


