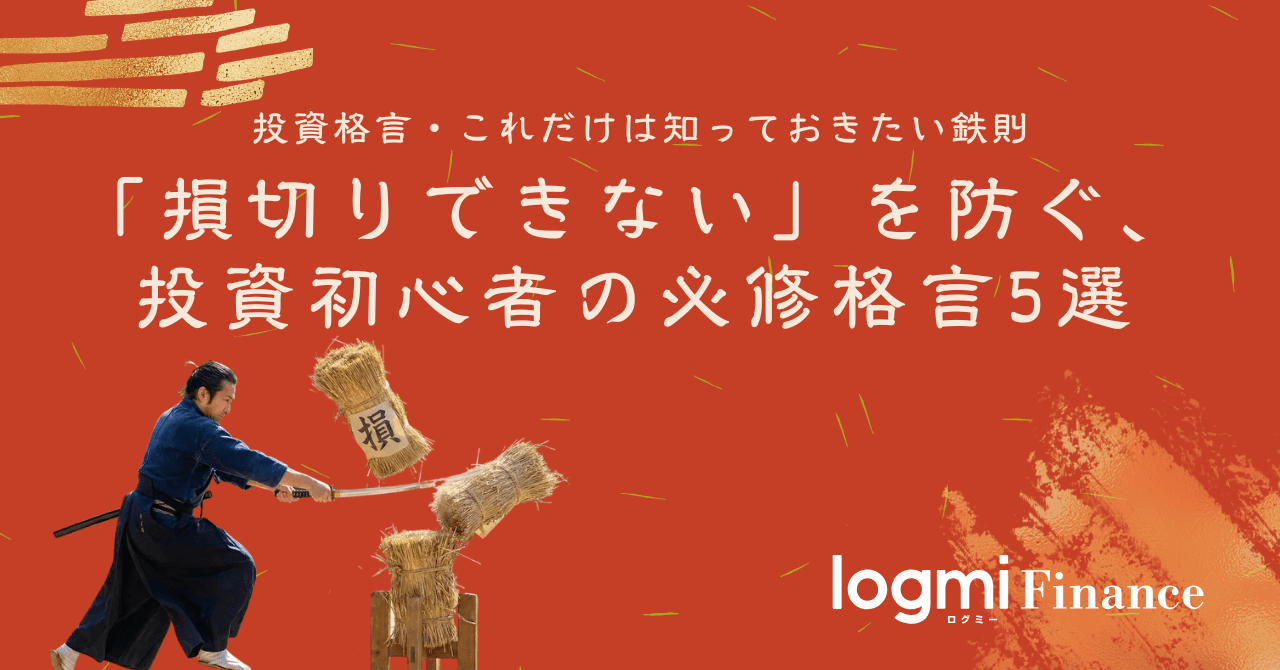【凄腕個人投資家たちの活動をのぞき見!】 保有株の“売り時”はどう決めていますか?
インタビューにご協力いただいた方々のご紹介(順不同・敬称略)
DAIBOUCHOU 氏(@DAIBOUCHO)
個人投資家。1973年生まれ。東京都在住。各企業の財務諸表分析を中心とした、割安成長株への超分散投資を得意とする。会社員時代の2000年に200万円の元手から株式投資を始めて、約4年で資産が大膨張して「億り人」になる。ところが、専業投資家になったとたんに、ライブドアショックやリーマンショックの影響で資産が大暴落。その後、安定重視の中長期投資にシフトして、資産10億円を達成。その投資経験や知見を個人投資家に伝え、株式投資の成功者を増やすことがライフワーク。会社四季報オンラインで「DAIBOUCHOU流 超分散投資」を連載中。著書に「DAIBOUCHOU式 新・サイクル投資法」(宝島社)がある。
個人投資家。1973年生まれ。東京都在住。各企業の財務諸表分析を中心とした、割安成長株への超分散投資を得意とする。会社員時代の2000年に200万円の元手から株式投資を始めて、約4年で資産が大膨張して「億り人」になる。ところが、専業投資家になったとたんに、ライブドアショックやリーマンショックの影響で資産が大暴落。その後、安定重視の中長期投資にシフトして、資産10億円を達成。その投資経験や知見を個人投資家に伝え、株式投資の成功者を増やすことがライフワーク。会社四季報オンラインで「DAIBOUCHOU流 超分散投資」を連載中。著書に「DAIBOUCHOU式 新・サイクル投資法」(宝島社)がある。
たけぞう 氏(@noatake1127
)
元証券ディーラー。証券ディーラー時代は、多い時に約10億円の資金運用を託され、重圧と戦いながら約50億円の収益を上げた。現在は個人投資家兼経営者でラジオやYouTube、TVなどに出演しセミナー講師も勤める。四季報オンライン、MONEY PLUSに記事を寄稿。いろはにマネーにて記事監修。メルマガとコミュニティでは毎日最新の株式情報を配信。
元証券ディーラー。証券ディーラー時代は、多い時に約10億円の資金運用を託され、重圧と戦いながら約50億円の収益を上げた。現在は個人投資家兼経営者でラジオやYouTube、TVなどに出演しセミナー講師も勤める。四季報オンライン、MONEY PLUSに記事を寄稿。いろはにマネーにて記事監修。メルマガとコミュニティでは毎日最新の株式情報を配信。
ちょる子 氏(@kabu_st0ck)
240万→2億を達成した平成生まれの兼業投資家。大企業営業→同社マーケティング→スタートアップで広報の立ち上げ→PR支援で独立。PR×IR×個人投資家で、企業さまの企業価値向上のお手伝いをしています。
240万→2億を達成した平成生まれの兼業投資家。大企業営業→同社マーケティング→スタートアップで広報の立ち上げ→PR支援で独立。PR×IR×個人投資家で、企業さまの企業価値向上のお手伝いをしています。
ヘム 氏(@pygmy_hem)
京都大学卒業後、総合商社に入社。社会人1年目より投資を始め、投資歴は27年になる。30歳で脱サラをし起業。現在も2社を経営する投資家兼会社経営者。390銘柄保有中、投資時価4.0億円(2025年2月28日時点)。個別銘柄分析&ポートフォリオ構成銘柄&成績をXで公開したところ、アカウント開設後、1年半でフォロワーが3万人突破。本当に価値のある会社に投資する「小型割安株」と「増配期待銘柄」を戦略の軸とし、さまざまなPFで構成した投資戦略。データを重視した投資手法で、その再現性の高さから、株クラ〜投資初心者まで幅広い支持を得ている。
京都大学卒業後、総合商社に入社。社会人1年目より投資を始め、投資歴は27年になる。30歳で脱サラをし起業。現在も2社を経営する投資家兼会社経営者。390銘柄保有中、投資時価4.0億円(2025年2月28日時点)。個別銘柄分析&ポートフォリオ構成銘柄&成績をXで公開したところ、アカウント開設後、1年半でフォロワーが3万人突破。本当に価値のある会社に投資する「小型割安株」と「増配期待銘柄」を戦略の軸とし、さまざまなPFで構成した投資戦略。データを重視した投資手法で、その再現性の高さから、株クラ〜投資初心者まで幅広い支持を得ている。
名古屋の長期投資家(なごちょう)氏(@Nagoya_Tyouki)
株式投資は95年12月から始めた超分散投資の長期投資家。インカムゲインと配当の成長を重視したPFを組んでいます。(2023年2月末時点では227銘柄保有)
株式投資は95年12月から始めた超分散投資の長期投資家。インカムゲインと配当の成長を重視したPFを組んでいます。(2023年2月末時点では227銘柄保有)
現在メインとしているご自身の投資スタイルについて、簡単に教えてください
DAIBOUCHOU 氏
小型株、PERが割安、ROE、ROA、ROICが高く安定的に成長する事業を行う会社に分散投資しています。フルポジ方針で30%程度信用取引で上乗せしています。
たけぞう 氏
現在は7割がスイング(2〜3日から1ヶ月月)です。3割はデイで実施しています。
ちょる子 氏
基本的にはマクロ経済や市場動向を分析して資産配分を決定し、その後に個別銘柄を選定するトップダウン・アプローチを行っています。今年のテーマは年初めは防衛・銀行(金利上昇)・物価上昇というところを見ており、夏ごろまではインバウンドでホテル業界や外国人ライクな日本発ラグジュアリーブランドも見ています。(1月春節は過去最多と聞いていたので、次の決算に期待しています。)あと、関税の話はありますが、自動車にも注目しています。セクターを決めたら基本的には一番時価総額が大きい銘柄に投資をしています。
ヘム 氏
私の投資スタイルは、企業の本質的な価値より割安に評価されている銘柄の中から、株価上昇のきっかけ(カタリスト)が見込める銘柄に分散投資するというものです。企業の本質的な価値と株価の差のことを「安全域」と言いますが、その差が大きい銘柄は小型割安株に多いため、私のポートフォリオは小型割安株が中心になっています。
割安な銘柄を見つけるために、私は以下の4つの方法を用いて評価しています。
資産価値と事業価値をもとに簡易的な理論株価を計算し、実際の株価と比較する。(目安として、理論株価が実際の株価の2倍以上の銘柄を選定)
PER・PBR・EPS成長率の3要素から割安度を判定する。
「Cash Neutral PER」(買収者視点での割安度指標)を用いて評価する。
EPS成長率と配当政策を仮定し、5年後・10年後のPER、PBR、配当利回り、理論株価を予測する。
このように、多面的に割安度を評価したうえで、十分に割安と判断できる銘柄を選定します。これは、あくまで一次予選のようなもので、ここで選ばれた銘柄について、次に株価上昇のきっかけ(カタリスト)があるかをチェックしていきます。
私の場合、カタリストの中でも特に「増配」に重きを置いています。増配は、株価上昇に直結しやすく、企業の成長を予測するよりも、増配継続の可能性を見極める方が容易だからです。もちろん、企業の成長性も分析しますが、投資判断においてどこに重点を置くかのバランスの問題です。
このようにして、「割安」かつ「株価上昇のカタリスト候補がある」銘柄に分散投資することで、市場を上回るリターンを狙っています。
割安な銘柄を見つけるために、私は以下の4つの方法を用いて評価しています。
資産価値と事業価値をもとに簡易的な理論株価を計算し、実際の株価と比較する。(目安として、理論株価が実際の株価の2倍以上の銘柄を選定)
PER・PBR・EPS成長率の3要素から割安度を判定する。
「Cash Neutral PER」(買収者視点での割安度指標)を用いて評価する。
EPS成長率と配当政策を仮定し、5年後・10年後のPER、PBR、配当利回り、理論株価を予測する。
このように、多面的に割安度を評価したうえで、十分に割安と判断できる銘柄を選定します。これは、あくまで一次予選のようなもので、ここで選ばれた銘柄について、次に株価上昇のきっかけ(カタリスト)があるかをチェックしていきます。
私の場合、カタリストの中でも特に「増配」に重きを置いています。増配は、株価上昇に直結しやすく、企業の成長を予測するよりも、増配継続の可能性を見極める方が容易だからです。もちろん、企業の成長性も分析しますが、投資判断においてどこに重点を置くかのバランスの問題です。
このようにして、「割安」かつ「株価上昇のカタリスト候補がある」銘柄に分散投資することで、市場を上回るリターンを狙っています。
名古屋の長期投資家(なごちょう)氏
PBR1倍以下のバリュー株への超分散長期投資です。
保有銘柄の売り時をどのように決めていますか?
DAIBOUCHOU 氏
特に売りのルールはありません。銘柄と状況次第で個別判断しています。株価が上昇し、すでに割高になった段階で、株価が天井付けたと考えたら売ります。買った後、相対的に弱いと考え直しても売ります。売り時で失敗と判断する人は、多くは売り時ではなく、うまく売却しないと儲けられない銘柄、売買タイミングに過度に依存していて、その銘柄にたいした魅力が無いのに買っているのが原因だと思っています。要は、銘柄選びの問題を売り時の問題にすり替えていると思っています。
たけぞう 氏
プラスをいかにして伸ばすかを考えています。マイナス収支の場合は一度売却して再度買い直して、ロスカットは早めに対処しています。
ちょる子 氏
タイミングですが、個別銘柄に関してはボリンジャーバンドとRCIで見ていて、RCIの短期が95を超えてくる&ボリンジャーバンドの日足+3σに来たタイミングで売却注文をします。上昇100日下げ3日という格言があるとおり、天井はわかりませんが、それなりにヒストリカルPERで見た時にも逸脱していたら売り時かと思いますし、その後さらに上げていっても気にしないようにしています。
3月11日には、優待銘柄で買っていたすかいらーくを売却しました。
3月11日には、優待銘柄で買っていたすかいらーくを売却しました。
ヘム 氏
私の売却基準は、「増配期待の低下」と「割安度の低下」の2つです。私は、増配期待が高く、割安な銘柄に投資するスタイルをとっているため、売却の判断も「増配余力が低下した時」や「株価が上昇して割安度が薄れた時」になります。
現在の市場では、東証改革の影響で企業の株主還元が強化されており、増配を重視する企業が増えています。そのため、EPS(1株当たり利益)の成長を上回るペースで配当を増やす企業が増えており、増配によって株価が上昇し、バリュエーション(PER)が高まるケースが多くなっています。
しかし、配当性向(利益のうち配当に回す割合)が上昇しすぎると、将来的な増配余力が低下するため、私はこの点を売却のシグナルとして重視しています。
売却の具体的なプロセスは以下のとおりです。
1.数値基準で売却候補を選定
まず、以下の基準をもとに、売却候補をリストアップします。
・配当性向が50%以上(増配余力が低下)
・PERが12倍以上(バリュエーションが割高)
・ 配当利回りが3%以下(投資妙味が薄れる)
※この基準はあくまで目安であり、市場環境によって調整することもあります。
2.定性分析で最終判断
次に、売却候補となった銘柄について、以下のポイントを定性分析し、最終的な売却判断を行います。
・業績成長の継続性(EPSが今後も成長するか)
・配当政策の持続可能性(増配が今後も続くか)
・市場環境や業界トレンド(外部要因が株価に与える影響)
ただし、直近の株価が上昇傾向にあり、EPSの成長期待が大きい場合は、モメンタム効果を考慮して売却を遅らせることもあります。このような場合、PERの上昇はある程度許容しつつ、株価の上昇トレンドが続く限りはホールドすることもあれば、一部の保有株を段階的に売却していく(売り上がる)こともあります。
一方で、EPSが成長せず、横ばいまたは減少しているのに、配当だけが増えている場合は注意が必要です。このようなケースでは、配当性向が上昇し続け、最終的に増配が限界に達する可能性が高くなります。特に、EPSが低下し、減配に至った場合は、株価が大きく下落するリスクがあるため、そうなる前に撤退することを意識しています。
現在の市場では、EPSの成長度合い以上に増配を実施する企業が増えているため、増配期待の変化を見極めることが重要です。そのため、従来よりも売却・銘柄入れ替えの頻度を高めることが、リターンを向上させるカギになると考えています。
現在の市場では、東証改革の影響で企業の株主還元が強化されており、増配を重視する企業が増えています。そのため、EPS(1株当たり利益)の成長を上回るペースで配当を増やす企業が増えており、増配によって株価が上昇し、バリュエーション(PER)が高まるケースが多くなっています。
しかし、配当性向(利益のうち配当に回す割合)が上昇しすぎると、将来的な増配余力が低下するため、私はこの点を売却のシグナルとして重視しています。
売却の具体的なプロセスは以下のとおりです。
1.数値基準で売却候補を選定
まず、以下の基準をもとに、売却候補をリストアップします。
・配当性向が50%以上(増配余力が低下)
・PERが12倍以上(バリュエーションが割高)
・ 配当利回りが3%以下(投資妙味が薄れる)
※この基準はあくまで目安であり、市場環境によって調整することもあります。
2.定性分析で最終判断
次に、売却候補となった銘柄について、以下のポイントを定性分析し、最終的な売却判断を行います。
・業績成長の継続性(EPSが今後も成長するか)
・配当政策の持続可能性(増配が今後も続くか)
・市場環境や業界トレンド(外部要因が株価に与える影響)
ただし、直近の株価が上昇傾向にあり、EPSの成長期待が大きい場合は、モメンタム効果を考慮して売却を遅らせることもあります。このような場合、PERの上昇はある程度許容しつつ、株価の上昇トレンドが続く限りはホールドすることもあれば、一部の保有株を段階的に売却していく(売り上がる)こともあります。
一方で、EPSが成長せず、横ばいまたは減少しているのに、配当だけが増えている場合は注意が必要です。このようなケースでは、配当性向が上昇し続け、最終的に増配が限界に達する可能性が高くなります。特に、EPSが低下し、減配に至った場合は、株価が大きく下落するリスクがあるため、そうなる前に撤退することを意識しています。
現在の市場では、EPSの成長度合い以上に増配を実施する企業が増えているため、増配期待の変化を見極めることが重要です。そのため、従来よりも売却・銘柄入れ替えの頻度を高めることが、リターンを向上させるカギになると考えています。
名古屋の長期投資家(なごちょう)氏
以下のような時には売却をしています。
・他に欲しい株ができて換金する必要がある時(予め売却候補の順位をつけておく)
・自分の予想とぜんぜん違う業績だった時
・今後暫く業績が低迷しそうな時
・株価が上がり過ぎて四六時中気になってしまう時
・他に欲しい株ができて換金する必要がある時(予め売却候補の順位をつけておく)
・自分の予想とぜんぜん違う業績だった時
・今後暫く業績が低迷しそうな時
・株価が上がり過ぎて四六時中気になってしまう時
今回は凄腕投資家のみなさんに、保有株の売り時についておうかがいしました。ログミーFinanceでは幅広い業界の決算説明会やIRセミナー、株主総会などの書き起こし記事を掲載していますので、ぜひご活用ください!